
織姫と彦星が年に一度会うことができる日
なぜ七夕は2つある?7月7日と(2025年は)8月29日
短冊に願いを書く七夕、この七夕が一年に2回あることは、よく知られています。
7月7日の日と旧暦の7月7日(伝統的七夕と呼ばれる日)です。
では、なぜ2回あるのか?
7月7日は七夕ですが日本のいまの暦では梅雨の最中。
せっかく一年に一度しか会えない織姫と彦星が雨であったり、曇っていては残念でなりません。
そこで『伝統的七夕』と言われる旧暦の7月7日(に近い日)とする七夕が2001年から国立天文台が報じ始めました。
定義としては、古代中国で生まれた二十四節気と言う暦、いまでもよく使われる「春分」や「秋分」「夏至」に「冬至」などもこの二十四節気のひとつですが、その中の「処暑」を含む日か、それ以前に近い朔(新月)の日から7日目であり2025年では8月29日、翌2026年では8月19日となります。
なぜいまの暦ではないのか?
では、なぜいまの暦ではダメなのでしょうか?
上でも触れましたが現在の暦の7月7日は梅雨の最中になることが多いです。
また、いまの暦では月の明るさがその年によって変わってしまいます。
2025年の7月7日は月齢11.7(正午の月齢)となっており、満月の数日前のとっても明るい夜空となります。
実際にこの日は織姫(こと座のベガ)と彦星(わし座のアルタイル)は見えていたものの、天の川は肉眼で見ることができませんでした。

しかし、伝統的七夕は旧暦を使うことから梅雨の開けた後となるため、満天の星空が見られる確率がグッと上がります。
さらには、月の明かりも伝統的七夕では旧暦、つまり月をもとにした暦となるため、7日の日は必ず半月より少し細い月となり、よる9時頃には沈むので天の川をはじめとした星々がの輝きを楽しむことのできる環境と言えます。
とは言え、8月に入ると台風などの影響も出始めるため一概には言えませんが。。。
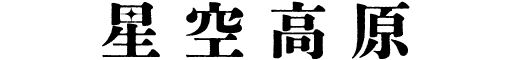
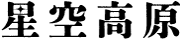
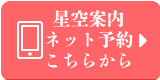
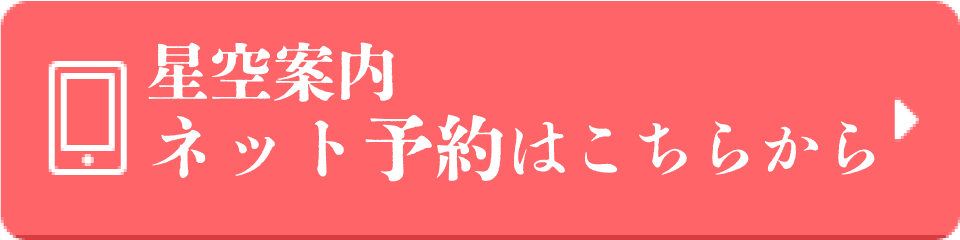

コメント